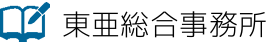帰化申請・入管手続(ビザ・在留・永住)・相続・韓国家族関係登録関連全般の総合サイトです。
大阪出入国在留管理局神戸支局(神戸入管)すぐ近く!
帰化申請
神戸を中心に全国各地で豊富な経験・実績の帰化申請手続!! 書類の取寄せから法務局対応、申請受付、面接、許可後まで完全サポートいたします。
- 帰化申請のことなら、圧倒的実績の東亜総合事務所へ
- 帰化申請の条件及び手続案内 step1.帰化申請の進め方 step2.必要書類を把握 step3.必要書類の集め方
-
韓国証明書類の取得・翻訳
[基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・新養子入養関係証明書・除籍謄本等] - 使用するフォーマット(様式・サンプル)
帰化申請のことなら、圧倒的実績の東亜総合事務所へ
東亜総合事務所はお客様の利益を第1優先に考えています。
◆帰化申請手続きは、本当に難しいものでしょうか?◆
答えは「ノー」です。
帰化申請が難しいとされているのは、その要件を充たすことが困難なだけなのです。
このサイトをご覧頂ければ、時間とわずかばかりの知識、労力があれば、帰化申請が、専門家以外の方でもできるものであるとご理解いただけると思います。
確かに、たくさんの書類を集めたり、関係官公署に出向いたりと手間はかかりますが、法律を知らなくても、事実に則したことを、法務局が用意してくれた書類に記載するだけです。(母国語がわからない方は、翻訳のみ苦労があるかと思います)
唯一、自分自身の言葉で思いを書かなければならないのが「帰化の動機書」ですが、これも小学校の作文程度書ければ十分です。(特別永住者は不要)
ですので、時間や手間など問題ない方は、ぜひ当サイトを有効活用なさって、ご自身でチャレンジなさってください。
ただし、仕事で平日時間が取れない、または、諸事情によりお急ぎの場合、要件について不安がある場合は、ぜひ、実績、信頼をモットーとしている私にお任せください。(特に要件については、一度無料相談をお試しください)
お客様には、迅速・安心・丁寧に応対するよう心掛けています。
さらに一歩進めて、人生で数少ない申請を、「楽しく」進めていただけたらと願っております。
低価格のみの売り文句で「安かろう・悪かろう」は一切提供いたしません。お客さまの時間・手間・費用すべてのコストの面から、ご満足していただけることをお約束いたします。
〜帰化申請については、豊富な経験・実績の東亜総合事務所におまかせください。〜

◆帰化申請を東亜総合事務所に依頼するメリット◆
◇法務局対応から申請受付、面接、許可、その後まで完全サポート
(事務所代表が、責任をもって法務局に取り次ぎます)
◇官公署の発行する書類は、一切当行政書士事務所が取得します。
(お客さまに手間と時間をとらせません)
◇本国の書類収集・翻訳もワンストップで行います。
(時間と費用の節約に努めます)
◇お客さまには、最初のインタビューのみお時間頂戴します。
(お客さまのお時間が許せば、いつでも遊びにきてください)
◇例外的な事件発生時以外、当初の見積もり以上の報酬は一切いただきません。
(身分関係の訂正・裁判等が必要になった事案など)
◇万一不許可になった場合は、全額返金いたします。
(ただし、申請受付以降、お客さまの責に帰する場合を除く。例えば当事務所に虚偽の説明をしたり重大な事実を告知しなかった場合。受付日以降、飲酒運転で検挙された場合など)
◇お急ぎの方でも大丈夫。業界トップレベルの時間で手続いたします。
~何よりも豊富な経験から帰化や相続にかかわらず、どのようなことでもご相談していただけます~
【トータルコストに自信があります!!】
給与所得者世帯【143,000円】
事業主・法人役員世帯【176,000円】
[追加報酬]
配偶者等成年者【55,000円追加】
幼児・学生の子【33,000円追加】
上記の報酬には、一切の書類収集・翻訳料等が含まれています。
《参考例1》
サラリーマン世帯(夫・妻・13歳の子・17歳の子)4名の場合
143,000円+55,000円(妻)+33,000円(子)+33,000円(子)=264,000円
《参考例2》
法人役員世帯(夫・妻・18歳の子・夫の両親)5名の場合
176,000円+55,000円(妻)+33,000円(子)+105,000円(両親)=369,000円
なお、別世帯でも、同時申請は可能です。
《参考例3》
兄弟姉妹などで、≪参考例1≫のような世帯構成(8名様)で同時申請を行う場合
基本報酬143,000円+55,000円×3人+33,000円×4名+22,000円(別世帯加算)=462,000円
=お一人様あたり 57,750円
当行政書士事務所は、最高品質の業務を必要最小限の費用でお客様に提供させていただいております。お見積りは、お気軽にどうぞ!(お客様のコストがもっとも低くなるよう、提案させていただきます)詳しくは、当事務所料金表をご覧ください。
※ 気になる報酬額についてはこちら ⇒ クリック
【ご依頼から許可までの流れ】
- 事前相談(無料)、お見積提示
- ご依頼⇒受任(着手金、総報酬額の25%〜50%を頂戴します)
- インタビュー、委任状にご署名・捺印いただきます。
- 書類収集・作成
- 法務局書類確認
- 申請日時打ち合わせ
- 申請受付(法務局同行いたします。無事受付受理されましたら、報酬残金頂戴いたします)
- 面接
- 許可決定
以上のような流れで申請を行います。
お客様には、申請受付・面接・許可証受領時に、法務局に足をお運びいただきます。
帰化申請の条件及び手続案内 step1.帰化申請の進め方 step2.必要書類を把握 step3.必要書類の集め方
〜これをご覧になれば、帰化申請の全体像がわかります!〜 帰化申請の手続概要を惜しみなく公開いたします。ご自身でチャレンジする方必見です!
帰化申請は難しいものでしょうか?
申請の全体像が見えれば、不安も軽減・解消されるでしょう。
多くの申請を手掛けてきた専門家がすべてのノウハウを提供しますので、どうぞご利用してください。
まずは、最低限の申請要件を確認いたしましょう。
次の条件にひとつでも該当しなければ、申請はできません。
ただ、該当するかしないか判断に困るケースもあると思います。
また、特別永住者や日本人の配偶者である方等については、一部要件が緩和されています。
不明な点は、法務局または当事務所までお気軽にお訊ねください。
帰化の条件
国籍法第5条第1項
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
※主に帰化申請をお考えの在日の方についてはまず問題ないでしょう。
ただし、婚姻や、長期の出張等で、長期間日本を離れている場合は、住所が日本に残っている状態であっても、実態として在留期間が中断していると判断されるケースがあります。 - 18歳以上で本国法によって能力を有すること。
※親(一方でも可)と一緒に申請する場合は、当然未成年の方でも可能です。 - 素行が善良であること。
※前科や交通違反歴、納税状況などから判断されます。 - 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
※給与所得者(いわゆるサラリーマンなど)は、ほとんど問題ないと思われますが、自営業の方については、確定申告の内容が障害となるケースが散見されます。
とりたてて裕福である必要はありませんが、常識的に生活を維持できるだけの収入又は資産が必要です。 - 国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと。
※韓国、朝鮮籍の方については、他の国籍を取得した場合には、反射的に本国の国籍を失いますので、問題はありません。 - 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
※説明するまでもない要件です。韓国民団や朝鮮総連は、上記の団体に該当しませんが、過去の活動内容や現在団体幹部である場合、お子様が現在民族学校に通学している場合等には、問題視されるケースがあります。(帰化意志の有無などの観点から)
さて、実際に帰化申請を進めていくにあたり、大まかな流れを説明します。
申請エリアや管轄法務局によって、若干の差はありますが、一般的には下記のとおりです。
- 1.帰化申請を決意
- 2.住所地管轄の法務局に相談
・原則事前予約が必要ですので、必ず管轄法務局の国籍課もしくは国籍担当部署まで電話で確認してください - 3.法務局の国籍課や国籍担当窓口で相談。申請に必要な収集書類の指示を受け、また、申請書の書式をもらいます(数回に分けて指示される場合もあります)。
- 4.上記で指示された書類を収集および作成のうえ、再度法務局に相談に行きます。
- 5.申請書類等に不備がないか確認してもらいます。
- 6.不備がなければ申請受付
・確認と受付を同時に行ってもらえるかどうかは管轄法務局によります。
・通常は受付に至るまで、少なくとも3~4回以上の書類点検を受けることが多いようです - 7.申請受付には、申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、申請書に署名、宣誓を行い、受付をしてもらいます。また、ここで、申請中の注意点等の指示を受けます。
・受付票が交付されますので、紛失しないように! - 8.3か月前後(法務局の申請受理件数等により差はあります)で、法務局より面接日時の調整の打診が電話連絡であります。
※最近では、面接まで6か月前後かかるとアナウンスされています。 - 9.申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、面接を行います。
・年齢、経歴、職業、身分関係等により面接時間には差があります。
・一般的に、学生さんや若年層については最短15分くらいで済むこともありますが、概ね1時間程度を見ている方がよいでしょう - 10.面接後4~6か月程度で結果が出ます。
・特別永住者については、受付から8か月前後が目安と思われます。
・結果が法務局より電話連絡にてあります。※最近審査期間が長期にわたるケースもあります(法務局では長い方は2年~3年かかるケースもあるとアナウンスされています)。 - 11.法務局に出向き、許可証、市区町村提出の帰化届の用紙を受け取ります。
- 12.在留カード又は特別永住者証明書の返納、帰化届の提出を行い、戸籍・住民票の編製を行います。
- 13.氏名や本籍の変更に伴う書き換え
(運転免許証や医師免許、看護師免許などの国家資格の証明など)を行います。 - 14.手続き完了です。お疲れ様でした!

どうでしたか?おおまかな流れを理解していただけたでしょうか?
ただし、ここで紹介した申請の流れは、申請条件や身分関係等に問題がないケースを想定しています。
平均的に、法務局に足を運ぶ回数は、5〜6回程度と聞いています。
申請にあたっては、下準備が時間、手間の節約に大変重要です。
当ホームページを可能な限り、活用してください。
ステップ2 必要書類を把握しましょう。
帰化申請は、職業(給与所得者・自営業者・法人経営者)によって提出書類が大幅に変わります。特別永住者である在日韓国・朝鮮の方を例にして、必要書類を解説します。
※括弧の中は、書類取得先を記載しています。
※神戸地方法務局管内を基準としています。
共通書類
- 帰化許可申請書(法務局様式。証明写真5㎝×5㎝貼付)
帰化許可申請書(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 親族の概要を記載した書面(法務局様式)
両親・子・兄弟姉妹・配偶者・配偶者の両親・内縁の夫(妻)・婚約者・申請しない同居の親族を記載。それぞれ生年月日、住所、連絡先、職業等を記載
親族の概要(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 履歴書その1(法務局様式)
出生から現在に至るまで、住所歴、学歴、職歴、身分関係の変動を時系列に記載
履歴書その1(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 履歴書その2(法務局様式)
海外渡航歴、保有資格、賞罰、使用言語を記載
履歴書その2(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 基本証明書 (기본증명서) ※(5〜10は本国または領事館で取寄せ)
被証明者の出生や死亡、改名、訂正などの事項が記載されています。申請者各自に必要
※平成20年1月1日以降に父母の死亡申告があるときは、父母の基本証明書も必要 - 家族関係証明書 (가족관계증명서)
被証明者の親・配偶者・子が記載されています。申請者各自及びその父母について必要 - 婚姻関係証明書 (혼인관계증명서)
被証明者の婚姻事項が記載されています。申請者各自及びその父母について必要 - 入養関係証明書 (입양관계증명서)
被証明者の養子縁組事項が記載されています。申請者各自に必要 - 親養子入養関係証明書 (친양자입양관계증명서)
被証明者の親養子縁組事項が記載されています。申請者各自に必要 - 除籍謄本 (제적등본)(本国または領事館)
父母の婚姻・死亡事項の記載あるもの ※神戸地方法務局管内では、父母の出生時までの除籍謄本が必要とされています。 - 上記5〜10までの翻訳文(翻訳者の住所・氏名・翻訳年月日を記載)
- パスポート・渡航証明書の写し(失効したものを含む)
写真が貼付されたページ、出入国により証印されたページ等、
白紙のページ以外をもれなくコピーします。 - 出生届記載事項証明書(出生届が提出された市区町村)
取得不能のときは、保管していないことの証明書を取得します。
前記6番の父母の家族関係証明書または10番の除籍謄本で証明できない兄弟姉妹については、その該当者の出生届記載事項証明書も必要 - 死亡届記載事項証明書(死亡届が提出された市区町村)
父母で日本国内で死亡した者がいる場合、提出を要します。
※2025年から不要とする取り扱いになっている法務局もあります。 - 婚姻届記載事項証明書(婚姻届が提出された市区町村)
申請者本人、両親のものが必要です。ただし、配偶者が日本人のときは不要(※配偶者の日本の戸籍謄本等により婚姻事実を確認します)。 - 離婚届記載事項証明書(離婚届が提出された市区町村)
過去に離婚歴がある場合、申請者本人、両親のものが必要です。
ただし相手が日本人の場合は上記と同様不要。 - その他養子縁組・認知等の記載事項証明書等(該当事実がある場合)
- 日本の戸籍・除籍謄本(本籍地の市区町村)
1.配偶者や子が日本人の場合(戸籍謄本)
2.親・子・兄弟姉妹・配偶者で帰化した者がいる場合(帰化事項が記載されているもの。転籍や改製などによって、現在戸籍に帰化事項の記載なき場合は、除籍謄本または改製原戸籍) - 住民票(住所地の市区町村)
世帯全員、1番詳しいもの(マイナンバー記載除く) - 閉鎖外国人登録原票(法務省秘書課個人情報保護係)
申請者・同居者について必要。※平成26年2月より取得不要となりました! - 生計の概要その1(法務局様式)
月単位の収入・支出を記載します。
生計の概要その1(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 生計の概要その2(法務局様式)
所有不動産・預貯金・有価証券・高価な動産について記載します。
生計の概要その2(PDF) 書き方サンプル(PDF) - 自動車運転免許証の写し(表裏両面)
- 運転免許経歴証明書(自動車安全運転センター)
違反経歴等が記載されているものです。過去5年間の経歴にチェックし、郵便局で請求します。
申請書は法務局に相談に行った際にもらうことができますし、交番、警察署にもあります。 - 土地・建物登記事項証明書(法務局)
住居等及び資産として不動産を所有しているときに必要
※2025年から不要とする取り扱いになっている法務局もあります。 - 不動産賃貸借契約書
住居が賃貸の場合必要 - 生徒手帳(学生証)または通知表の写し
申請者に学生の方いる場合必要 - 帰化の動機書
帰化の動機書(PDF)※特別永住者は不要です
■上記に加え、職業別に、下記の書類が必要です。
【サラリーマン・パート(給与所得者)の場合】
1. 直近1か月分の給与明細書又は在勤・給与証明書(お勤めの会社)2. 直近1年分の源泉徴収票(お勤めの会社)
3. 直近1年分の市民税納税証明書(完納分)・非課税(所得)証明書(市区町村)
※非課税の場合は非課税(所得)証明書2年分
※上記について世帯全員分が必要です。
4. 健康保険被保険者証、健康保険組合員証等
【自営業者(個人事業主)の場合】
- 事業の概要を記載した書面(法務局様式)
事業内容、開業年月日、従業員数、1年間の収支、負債、取引先などを記載 - 直近の確定申告書控え(収支内訳書含む)の写し
原則税務署の受付印があるものが必要 - 直近2年分の所得税納税証明書その1、その2(税務署)
その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。 - 直近2年分の消費税納税証明書(税務署)
消費税の申告がなくても、証明は必要 - 直近2年分の個人事業税納税証明書(県・府税事務所)
課税業者でなくても、証明は必要 - 直近1年分の市民税納税証明書及び課税証明書(市区町村)
※非課税の場合は非課税(所得)証明書2年分 - 直近1年分の源泉徴収金の納付書の写し(従業員がいる場合のみ)
8 さらに、自営業者等(国民年金法第7条第1項第1号に該当する方)については
年金定期便、年金保険料(直近1年分)の領収書等の写しが必要となります。
■国民年金保険料納付確認(申請)書 (法務局様式)
※管轄法務局により適宜ご使用下さい。
9 健康保険被保険者証、健康保険組合員証等
【法人経営者(役員)の場合】
- 事業の概要を記載した書面(法務局様式)
事業内容、開業年月日、従業員数、1年間の収支、負債、取引先などを記載
事業の概要(PDF) - 直近の法人税確定申告書控え及び決算書・貸借対照表の写し
確定申告書には、税務署の受付印があるものが必要 - 直近2年分の法人税納税証明書その1、その2(税務署)
その1は納税額、その2は所得額を証明するものです。 - 直近2年分の法人消費税納税証明書(税務署)
- 直近2年分の法人事業税納税証明書(県・府税事務所)
- 直近1年分の法人市民税納税証明書(市区町村)
- 直近1年分の法人県(府)民税納税証明書(県・府税事務所)
- 直近1年分の源泉徴収簿及び納付書の写し
- 直近1年分の年金・健康保険料の領収書写し
- 直近1か月分の給与明細書又は在勤・給与証明書(お勤めの会社)
- 直近1年分の源泉徴収票(お勤めの会社)
- 直近1年分の市民税納税証明書(完納分)・非課税(所得)証明書(市区町村)
※非課税の場合は非課税(所得)証明書2年分
以上が、帰化申請に通常必要となる書類です。
ただし、ケースによって、さらに追加を要する場合がありますので、法務局の指示にしたがってください。
例外的な書類の一例
年金生活者は年金の支給通知書や証券、預貯金で生活されている方は預貯金の通帳の写し、仕送りで生計を立てている方は仕送りしている方の所得の証明が必要となります。
■書類の収集・作成は短期決戦で挑みましょう!
帰化申請で、一番面倒なのが書類の収集です。
帰化をする!と決意したら、集中して書類の収集に努めましょう。
また、法務局に事前に相談に行かれる際でも、可能な限り必要書類を持参していくほうが、効率が大幅にアップします。
ステップ3 必要書類の集め方を伝授します。
膨大な量の帰化申請書類を収集・作成するには、事前の準備が重要です。
ご自身で帰化申請にチャレンジしようとされる方は、当事務所で行っている方法をぜひ参考にしてください。
- 1.まずクリアポケットファイルを準備します
100円ショップなどで購入できますね。申請人の数にもよりますが、40ポケット以上あるものが望ましいでしょう - 2.法務局にて必要書類を確認し、必要書類一覧表・提出書類の様式を取得します
- 3.必要書類一覧表の記載の順番に従って提出書類様式及び収集書類名を記載したメモをクリアポケットに差し込んでいきます
※様式は書き損じがあるときのために、コピーをとって余分に準備しておく方がよいでしょう。
※様式もメモも、1種類につき1ポケットを使用することで、抜けがなくなります。 - 4.時間がかかるものから収集を開始します
本国の家族関係証明書等や、遠隔地にある記載事項証明などは早めに請求します。
運転免許経歴証明書も請求から約10日前後と取得に時間がかかりますが、有効期間も短いですので、どのくらい受付までに時間がかかるか予想して、請求のタイミングを考えてください。 - 5.収集書類から、法務局の様式に転記すべきものは転記し、その他の書類も作成していきます
- 6.すべてのクリアポケットの中の様式への記載を終え、メモ用紙もすべて収集書類に差し替われば、ハイ!出来上がり♪
以上のとおり、クリアポケットファイルを活用すれば、簡単かつ一目瞭然に書類を整理することができます。
せっかく集めた書類をひとつの封筒に雑に放り込んだりしてしまって、抜けがあったり、逆に重複して取得し、余分な費用を使っているケースを大変よく見受けます。ぜひ参考になさってください。
■収集書類の有効期間も大事です。
せっかく集めた書類も、時間が経ちすぎてしまえば、使えなくなるものもあります。
ただし、帰化申請は、一般的に時間がかかるという前提で、他の許可申請と比べて、比較的有効期間が長めに設定されています。
代表的な書類の有効期間を例示します(あくまで目安とお考えください)。
- 本国の家族関係登録簿関係の書類…発給日から概ね1年間
- 住民票…概ね4か月
- 各種記載事項証明書…期限なし
- 運転免許経歴証明書…発行から約2か月
- 給与明細…直近月のもの
- 納税関係書類…次年度のものが発給可能になるときまで
また、書類の記載内容に変動があった場合は、当然に新しいものが必要となります。
■書類取り寄せ費用も馬鹿になりません!
官公署に支払う書類取得のための手数料も決して小さなお金ではありません。
別の書類と間違ったり、重複して同じ書類を取り寄せたり、有効期間を超過して、再度新たに取得するようなことになると、お金と時間の浪費になります。
参考までに、何点かの書類の必要手数料を挙げてみます。
- 戸籍謄本 【450円】
- 除籍謄本・改製原戸籍 【750円】
- 住民票 【300円】(ただし市区町村によって差あり)
- 市民税納税証明書・非課税(所得)証明書 【300円】(ただし市区町村によって差あり)
- 韓国除籍謄本・家族関係証明書等 神戸【130円】大阪【130円】(為替により変動あり)
- 各種記載事項証明書 【350円】
- 所得税・法人税・消費税納税証明書 1年度、1証明 【400円】
- 事業税・県(府)民税納税証明書 1通 【400円】(都道府県によって差異あり)
- 運転免許経歴証明書 【800円】
- 会社や不動産の登記簿謄本 【600円】
などなど・・・
事前に書類の確認を徹底しましょう!
電話番号:078-515-6610
『無料メール相談』

豊富な経験で困難と思われる申請も多く経験してきました。たくさんのお客様に喜んでいただいています。
◇◆◇対応可能エリア◇◆◇
当職が官公署に直接法務局に出頭し、申請のサポートをさせていただく通常対応エリアは、兵庫県下及び隣接府県となります。
その他エリアからの依頼についても対応可能ですが、日当、交通費が発生することもありますので、ご了承ください。
韓国証明書類の取得・翻訳
[基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・新養子入養関係証明書・除籍謄本等]
韓国籍の方については、帰化申請・相続手続ともに、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・新養子入養関係証明書・除籍謄本等の身分関係書類の取寄せ、翻訳が必要です。
帰化を申請するにあたり、申請者については
-
基本証明書(기본증명서)
基本証明書翻訳サンプル(PDF) -
家族関係証明書(가족관계증명서)
家族関係証明書翻訳サンプル(PDF) -
婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
婚姻関係証明書翻訳サンプル(PDF) -
入養関係証明書(입양관계증명서)
入養関係証明書翻訳サンプル(PDF) -
親養子入養関係証明書(친양자입양관계증명서)
親養子入養関係証明書翻訳サンプル(PDF)
上記に併せて申請者の両親についての
- 家族関係証明書(가족관계증명서)
- 婚姻関係証明書(혼인관계증명서)
の取寄せ・翻訳が必要となります。
なお、父母双方の除籍謄本(제적등본)の取得・翻訳も必要です。
帰化申請をするにあたり、韓国・朝鮮籍の方については、原則として、身分関係書類、除籍謄本が必要となります。
なお、身分関係が整理されていない場合については、現在のところ、その整理までは求められていません。
ただし、その場合でも、他の立証資料(日本国内における出生届や婚姻届、死亡届の写しなど)から客観的に身分関係を明らかにできないと、帰化後に編製されるべき日本の戸籍に実態に即した身分関係が記載されない恐れがあります。
また、収集が必要な家族関係証明書等につき、そもそもご自身の韓国家族関係登録簿が編製されているかどうか分からないというお客様も稀にいらっしゃいますが、もしパスポートをお持ちでしたら編製されているはずです。登録基準地(従前の本籍地)が判らない場合には、パスポートを作成した領事館で教えてもらうことができます。また、中高年の方で在外国民登録証をお持ちの方は、その中に旧戸籍の本籍地、戸主名等が記載されていますので、それで確認するのも一つの手です。
そして取得したハングル記載の除籍謄本や各種身分関係書類等の翻訳は、申請者本人、知人など誰が行ったものでも大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所・氏名を明記します。
また、相続手続にあたっては
- 被相続人の出生時まで遡る除籍謄本すべて
- 被相続人の基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書
- 法定相続人の基本証明書・家族関係証明書
の取寄せ・翻訳が必要です。
※当事務所での翻訳は家族関係登録簿関連の証明書 1通1,980円、除籍謄本(電算化)1頁あたり2,200円で承っています。
(10通(頁)以上の翻訳ご依頼で、翻訳代金合計から1割引させていただきます)
【 西紀・檀紀・朝紀 対照表 】
西紀1868年〜1951年を韓国年号に対応した表です。縦書の韓国除籍の翻訳の際にご利用いただけます。
ぜひご参考ください。
対照表 (pdf)
上記の書類を請求するには?
身分関係の書類の請求先は、本国か領事館いずれかになります。
本国に請求するのは稀でしょうから、領事館への請求が多いことと思われます。
ただ、全国にある韓国総領事館でも、即日発給してくれる領事館は限られています。
例えば、当事務所のすぐ近くの駐神戸総領事館に請求しますと、発給まで1週間程度の日数を要します。
しかし、駐大阪総領事館ですと、足を運べば、即日その場で発給を受けることができます。
というわけで、できるだけ早めに取得しようとする場合は、大阪に出向くのがよいでしょう。
請求に行く際には、在留カード(特別永住者証明書)または旅券を持参し、登録基準地(本籍地)を確認のうえ、出向くようにしてください。
(委任を受けて行かれる場合は、委任者の在留カード(特別永住者証明書)又はパスポートの写し、委任状、そして請求される方の身分証を持参してください。
翻訳を依頼するには?
まず考えられるのが、韓国民団でしょう。
韓国民団に依頼すれば、請求から取得、翻訳まで一貫して行ってくれます。
また、領事館でも発給窓口において、翻訳業者のリストを配布しています。
お住まいのお近くなど、ご都合の良い業者に依頼することもよいでしょう。
翻訳手数料は2,000円〜5,000円前後と思われます。
当事務所では、FAX・郵便でも翻訳の依頼を受け付けております。基本・家族・婚姻等の証明書は1通1,980円、電算化除籍謄本は1ページ あたり2,200円(電算化前横書2,750円・縦書3,300円)です。お気軽にお申し付けください。
※ 詳しくはこちらからご確認ください ⇒ クリック
※ただし、ハングルが読める方は、ご自身または知人の方が翻訳しても大丈夫です。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の住所、翻訳者の氏名を明記すれば足ります。
特別な資格は必要ありません。
ただし、大切な申請に使用するものですし、専門用語も多いですので、やはり専門家等に依頼するほうが無難かもしれません。
また、場所や氏名など、固有名詞も多く含まれていますので、労力がかかることも事実です(これまでの膨大な経験から当事務所は翻訳の精度に自信があります!)。
当事務所は、行政書士法により守秘義務が課せられておりますので、お客様からの相談、書類取得・翻訳上の知り得た情報は100%守ります。

また、スタッフ全員がハングルに精通しておりますので、不備のない手続、翻訳、韓国行政との交渉を迅速・確実に遂行いたします。
使用するフォーマット(様式・サンプル)
帰化申請で使用するフォーマットはこちらからダウンロードできます。
※ダウンロードするにはAdobe Readerが必要です。
帰化許可申請書(PDF)
書き方サンプル(PDF)
親族の概要(PDF)
書き方サンプル(PDF)
履歴書その1(PDF)
書き方サンプル(PDF)
履歴書その2(PDF)
書き方サンプル(PDF)
生計の概要その1(PDF)
書き方サンプル(PDF)
生計の概要その2(PDF)
書き方サンプル(PDF)
事業の概要(PDF)
帰化の動機書(PDF) ※特別永住者は不要です
※様式はご自由に活用していただいて結構ですが、サンプルの無断転用はお断りいたします。
申請書をはじめ、上記すべての書類は手書きでもまったく問題ありませんが、丁寧に記入するように心がけてください。お問い合わせ・ご予約は当行政書士事務所の無料メール相談フォームへ・・・
相談無料!事務所での直接面談の他、メール相談もお気軽に!
お問い合わせ・ご予約は当行政書士事務所の無料メール相談フォームへ・・・
相談無料!事務所での直接面談の他、メール相談もお気軽に!